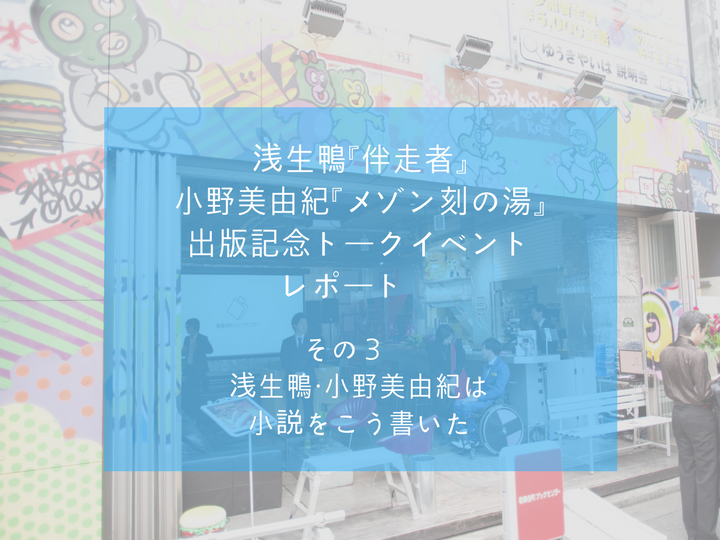
こんにちは。本が好き!編集部の和氣です。実は和氣のもうひとつの顔であるBOOKSHOP LOVERとして、2018年3月7日に開催したイベント「「みんなちがって、みんないい」? 多様性をテーマに語る日本のいま ~浅生鴨『伴走者』(講談社)・小野美由紀『メゾン刻の湯』(ポプラ社)出版記念 トークイベント~」のまとめを書きました。
全5回のうち、第3回目の記事です。
- 「多様性」っていう言うけれど…… 〜浅生鴨『伴走者』・小野美由紀『メゾン刻の湯』出版記念トークイベント・レポート その1〜
- 「自分が相手をどう思うか、と相手が自分をどう思うか」しかない 〜浅生鴨『伴走者』・小野美由紀『メゾン刻の湯』出版記念トークイベント・レポート その2〜
『伴走者』『メゾン刻の湯』ともに、献本プレゼントをさせていただいた作品なのでお読みになっている方も多いかとは思いますが、未読の方はぜひ両作を読んでからの方が楽しめると思います! 最高に面白い本です!
テレビ番組だからできること、本だからできること
小野 そのことについて浅生さんにお聞きしたいのが、浅生さんはメディアの作り手じゃないですか。でも番組を作ったりしていると、どうしても尺っていうものがあって簡単化しないといけない事って多分いっぱいあると思うんですけど、そういうことに関しては、ご自身の中ではどう感じられていますか?
浅生 テレビとCMと、自分でつくる映像作品とではまるで違うんですけど、言い方を間違うとすごい多くの人が怒りそうなんですが、少なくともテレビ番組っていうものは離乳食なんです。
小野 そう、表現するんですね!
浅生 どんな人でもすぐ食べられるように柔らかく砕いてあげていて。テレビ番組はそもそもが歯ごたえのないものなんですよ。
だから、多くの人がテレビを見て、テレビに対する文句を言ったり意見を言ったりするっていうのは食べられるからであって。本当に一流の専門家が難しい議論やってるのをテレビで流したら誰も意見を言えないんですよね、わかんないから、何言ってるか。
それを嚙み砕いて嚙み砕いて、一番食べやすく一番分かりやすい初歩の初歩まで落としてあげているのがテレビなので。そういう意味ではテレビはきっかけに過ぎない。
だから、そんなに僕は噛み砕くことに対して、わかりやすくしないといけないことに対してはあんまり気にしない。それをきっかけに「こっちの方向に進むといいよ」とか、「こういうものの流れがあるからもし興味があればこっからこっちに行ってごらん」みたいなベクトルは示すんですけど。基本的に最初の一口以上のことはテレビはやらないしできないですかね。
小野 なるほど。じゃあ他の表現形態でも活動されていらっしゃるのは何かそこに理由があるということですか?

浅生 射程距離が全然違うんですよね。それこそテレビ番組とかCMはマスに打つんですよ。普通に打っても数千万人とかに届くわけですよ。しかも短時間内に数千万人に届くのでインパクトはあるんですけど時間の距離が短い。つまり、3年後に影響するCMって多分ないんですね。
でも実は、書籍っていうのは三年後なんて全然余裕で、下手すれば、千数百年前の書物が未だに読まれているわけで、その時間を超えていく距離感っていうか射程感っていうか。それはやっぱり書物っていうメディアにしかできないんですよ。だから、自分とはまるで違う世代に問うているというか。そういうことが書籍には可能なので。書籍にはそういう面白さがありますよね。
小野 そうですね。
浅生 一冊の本で人生ががらりと変わることとかそうそうないと思うんですけど、ただやっぱり一冊の本を読むことで少し自分の人生に影響があることは誰しもある気がするんですよね。
でも、一本の CMが人の人生を変えるってなかなかない。もちろんCMを観て広告されていた商品を買ってずいぶん人生が変わりましたってことはあるのかもしれないけど、人生観そのものとか物の見方が変わるっていうのはやっぱり書物の方が強い気がする。
小野 すごく基本的な質問になるんですけど、多分インタビューとかでも聞かれているとは思うんですが、どうして今回、障害者スポーツをテーマに書かれたんですか?
浅生 単純に担当としてソチパラリンピックの CMをつくらなきゃいけなくて、それで、そのときにいろいろ調べていたら伴走者っていう存在に出会って、「伴走者おもしれえな」って思ったんですよ。「この人たち、超かっこいいな」っていうことなんですよね。
だから、伴走者の生きざまが面白くて、物語になる存在だなって思ったからです。実は障害者スポーツを題材にしたかったわけではないんですよね。
小野 伴走者自体を書きたかったっていうことですよね。
浅生 伴走者という存在。もちろん題材として障害者スポーツの伴走者を選んでるんですけど。以前、ソチのときに作ったCMが「伴走者になろう」っていうCMだったんですよ。パラリンピックを見て応援すること自体が、もうそれは伴走なんだよっていう投げかけをしたCMだったんですね。あらゆる人がなんらかの形で伴走者になれる。そこがこの小説の原点に多分あると思っています。
小野 伴走者として登場する人物が最初は伴走者になることを望んでいないっていうところがすごく面白いなあって思ったんですよね。伴走者になることに対して何らかの抵抗を見せたりとか。でも、そこから変わっていくっていうのが小説としての醍醐味を押さえてらっしゃっていると思いました。
それと、”伴走者。それは誰かを助けるのではなく、その誰かと共にあろうとする者”とか”俺は伴走者だ。そして、この人が俺の伴走者なんだ。”とか。その感覚がすごくいいなって思いながら読んでました。
浅生 フラットに生きようと思うとそうなるよねって思うんですよね。僕は元々物理学が専門なのでどうしても反作用っていうことを常に考えるんですけど。それは要するに、僕が本を持つという状態は、本が僕に押されているということと同時に本が僕を押してるっていうことが同時にここに存在してるということなんです。その両方があって本はここで留まっているわけですよね。
だからたぶん、伴走者と競技者の関係もお互いがお互いを押し合うことによってそこに存在できるんだろうなっていう。
そんなちゃんと考えて書いてないんですけどね。書くときはほとんど無意識で書いているので。
小野 でも、それってすごく理想的な形だなって思いました。
浅生 そこがたぶん小説でしかできないって思っています。どうしてもノンフィクションだとそこまでは言えない。ドキュメンタリーであっても思った通りのことなんて起きないので。「本当はもう一個こういうエピソードが起きてくれると、ここまでのことが言えるのにな」っていうのをドキュメンタリーでやったらヤラセって言われるのでそれはできない。
フィクションの強みはそこで、ドキュメンタリーではできないことを小説で書いているって感じですね。

小野 書く際に気を付けられた事ってありますか。
浅生 これはちょっと多様性の話から離れて完全に文章の話になっちゃうんですけど、『伴走者』では極力、比喩表現は直喩だけにして隠喩とか換喩は全部抜きました。
小野 それはなぜですか?
小説世界の中に入っていって取材する
浅生 読者には生でその場にいる感覚を体験して欲しかったので、ドキュメント感を出したかったんですよね。隠喩とか換喩って文芸=文章の芸、つまり、文章を美しくするための技術なんですよ。それが入るとドキュメント感が薄れるから。本当にカメラで撮って、撮れないことはもう抜いたって感じです。撮影できることしか書いてないという。
小野 だからこういう読み応えなんだって納得しました、読んでいて色の細やかな違いが描かれていたり、登場人物が感じてる身体感覚がすごく細やかに再現されてるなと思ったんです。浅生さん自身は身体感覚みたいなものは大事にされて書かれてるんですか。
浅生 ぼく、書くときって見たままを書いているだけなので実はそれほどでもないかもしれないんだけど……どういえばいいのかな。
頭の中でずっと小説世界を作って、人物がなんとなくできてきて、その人物が動き始めたら、自分の頭の中に入っていって、そこにカメラを置いて撮影して、で、戻ってきて、撮れたものを編集する、みたいな書き方なんですね。
本当に目の前で起きていることをメモってるというか。目の前で起きている会話を一生懸命聞き書きしてるみたいな感じなので。こういうこと言わせようとかこういうことやらせようとかではなくて、勝手に起きてる事を一生懸命メモっているだけだから、登場人物が感じていることを書いてるだけなんですよ。だから、意識して身体感覚の部分を際立たせようとかっていうんじゃなくて、たまたま彼がそこでそう感じていからそう書いたっていう。
『伴走者』は競技の話なので、マラソン篇はマラソンレースに出る。ゲレンデ篇の方も最後、大会に出る出ないみたいになるんですけど、実はラスト、結果がどうなるか僕も最後まで知らなかったんですよ。そのシーンを書くまで。最後の最後、その瞬間が来て「えっ、そうだったの!?」っていう。自分でも驚いたような感じなので。
あんまり細かいことは意識していないんですよね。見たままをいかに書くかっていう。で、つい書きすぎてしまったところをどれだけ削れるかっていう。削るのに苦労した感じですかね。気を抜くと文章を盛りたくなっちゃうというか、形容詞とか副詞とかいっぱい入れたくなるので。それをどこまで削れるかっていう。これ以上削ったらもう何も伝わらないかもしれないから、ギリギリ残すっていう。
小野 見たことない景色でも書けますか?
浅生 書けます。
小野 そうなんだ。私は読んでいて、例えば、スキーのシーンだと
”尾根を越えて届く光は七色に分かれたあと、再び涼介の前で混ざり合って白になる”
とか見たことない人は絶対書けないだろうって思ったんですけど、そうじゃないということですよね?
浅生 ぼくは頭の中のその場で見たわけですよね。見たことのないものを書けるわけではなくて、見たから書いているっていう感じですね。
小野 ビジュアルが強いんですね、浅生さんは。
浅生 たぶんずっと映像の仕事をしていたかからじゃないかな。僕は『メゾン刻の湯』を読んで、例えば倒置の使い方とか、文章の主語と述語の置き方がちょっと日本語離れしているかなって思うことが所々あって。
小野 本当ですか!
浅生 この文体はすごく面白いなって思って。なんでそういう文体になったのかっていう。うまく言えないんですけど、普通の日本語の人ではないこのリズム感をどうやって生み出したのか。
小野 すごいギクッとしました。小説を書くのが始めてだったので、やり方がわからなくて、最初フランス語で書いていたんですよ。で、フランス語で書けないときは英語で書いていたんです。それを日本語に翻訳して書いていたんですよ。
浅生 翻訳なんだ、これ! じゃあ外国文学?
小野 すごい馬鹿正直に言うと、私、小説の書き方が一切分からなかったから村上春樹さんの『職業としての小説家』を読んでそのまま真似しようと思って、真似したんですよ。自分の文体も分からないし、とりあえずフランス語で書いて翻訳してっていうのをやったからだと思うんですけど。それって日本語話者の人にとっては読みにくかったんじゃないかなって思ってすごいドキッとしました。
浅生 読みにくいというか、倒置とかがぽーんって入ってくるから、そこでなんかね、ギクッてするんですよ。
小野 そうですか。そっかあ。
浅生 それがすごい面白くて。
小野 いま自分がギクギクしているんですけど(笑)
浅生 いやいや、だから、ハッてする瞬間があって、普通に書いていたら案外流れていくような地の文に、ふって引っかかっていくようなフックがいっぱいある感じがして、すごい面白いなって思ったんです。これは小野さん独特の文体ですよね。
小野 私、いまでも自分の文体が分からないです。今回そうやってエチュード的に書いたけど、これが自分の文体かっていうと、それはちょっとよく分からないんですよね。ただ、浅生さんと違うところは私はすごく比喩フェチです。
浅生 一つの名詞に二つ比喩を入れたりとかしますよね。
小野 宮沢賢治とかフィッツジェラルドとかがすごい好きなんで、とにかくその世界に近づけたいなと思って比喩を頑張ったっていう感じです。それにしても自分の考えを人の前にさらさなきゃいけないのってすごい恥ずかしいですね。
浅生 それがトークイベントってやつですよ。
小野 あはは、そっか(笑) そういう感じですね。
(その3は本が好き!通信にて2018年4月14日公開予定)


